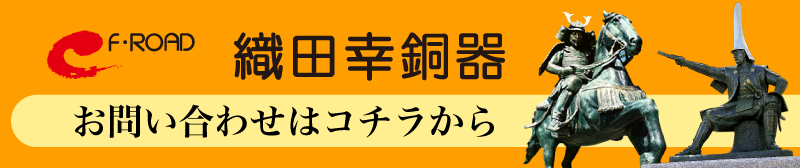高岡銅器発祥の地は千保川沿いの金屋町です。 その歴史は、今から約400年前に遡ります。 加賀藩二代目藩主前田利長は慶長14年(1609)に高岡城に入城。 城下の発展のため、近郷から鋳物師(いもじ)7人を呼び集め、千保川左岸に5カ所鋳物工場を開きました。
諸役を免除された手厚い保護のもとで、金屋町の鋳物は大きく発展し、現在の高岡銅器の発展の礎となっていったのです。 江戸時代中頃には、仏具などの鋳造も盛んになり、明治から昭和の初期には、各国の博覧会にも出品されました。 昭和50年(1975)には、日本初の国の伝統工芸品産地の指定を受け、銅鋳物の一大産地として、今日まで幅広い製品が生み出されています。
高岡銅器・製造工程
鋳物が完成するまでには、いくつもの工程があります。原型・鋳型をつくり。地金を流し込んで型から取り出す。削り磨いて着色し、品物によっては彫金、象嵌を施して仕上げとなります。古くは数人で一貫してすべての工程をこなしましたが、明治以降から徐々に専門化し、各分野の技術も向上、生産量も高まってきました。


図案や写真をもとに、原型作家が粘土で原型を作ります。その後、鋳造用の石膏へ移しかえます。これを石膏原型といいます。

銅や錫などを坩堝(るつぼ)で溶かし、型に流し込みます。流し込んだ合金が固まったら、型をばらします。これを「型ばらし」といいます。

鑢(やすり)や鏨(たがね)を使い、手作業によって丁寧に削り、原型に忠実に再現します。これを「手仕上げ」といいます。

腐食防止と化粧を重ねて表面を着色します。「おはぐろ」「いぶし」「青銅色」など、伝統的な着色法があり、これらは「古代色」とも言われます。

完成です。ものによっては、仕上げの後に、表面に模様を施す「彫金」や、別の金属をはめ込む「象嵌」などの加工を施すこともあります。